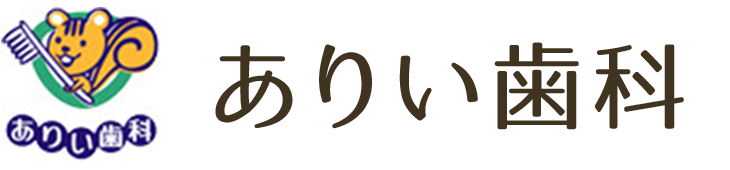こんにちは。ありい歯科院長の有井です。
ぐんぐんと気温も上昇し、梅雨が明けたことで夏真っ盛りになってまいりましたね。
暑い夏は特に生活リズムや食生活のリズムの崩れから、体に不調をきたすかたも多いですよね。
そこで今回は、特に夏に気を付けていただきたいお口の健康についてお知らせいたします。
まずはお口の健康をしっかり保ち、暑い夏を一緒にのりきっていきましょう。

夏の生活で、歯の健康に気を付けるポイントには以下のようなものがあります。
夏の歯の健康ポイント
① 水分補給と酸性飲料の摂取
暑い季節には水分補給が大切ですが、スポーツドリンクや炭酸飲料などの酸性飲料を摂りすぎると歯のエナメル質を傷つける可能性があります。水を主体にして、酸性飲料は控えめにしましょう。

② アイスクリームや冷たい食べ物
冷たい食べ物や飲み物は、歯の敏感さを引き起こすことがあります。過度に冷たいものを一気に食べたり飲んだりしないように注意しましょう。
③ 糖分の摂取
夏はアイスクリームやかき氷などの冷たく甘いものを摂取する機会が増えます。これらは虫歯の原因となるため、食べた後はすぐに歯磨きをするか、口をすすぐように心がけましょう。
④ 歯のケアを怠らない
夏の旅行やアウトドア活動が増えると、普段の歯のケアを怠りがちです。旅行中でも歯ブラシを持ち歩き、毎食後に歯を磨く習慣を続けることが大切です。

⑤ お口の乾燥を防ぐ
暑さで口が乾燥しがちになると、唾液の量が減少し、虫歯や口臭の原因となります。こまめに水を飲み、口の中を潤しておくことが重要です。
⑥ 定期検診
特に旅行や長期の外出前に検診を受けると安心です。お口のトラブルの心配なく思いっきりレジャーを楽しむためにも事前の受診をお勧めしています。
大きく6つのポイントをお伝えしましたが、できるところから意識して始めてみてくださいね。
長期休暇前は、例年当院でもご予約が混み合う可能性が高いため、急に「困った!」「どうしよう!」とならない様に早めの歯科医院受診をお勧めいたします。
お口の健康と体の健康を大切に、暑い夏もしっかりと乗り切っていきましょう。